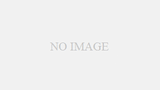インターネット上に書き込まれた悪口や中傷によって、心を傷つけられたり、企業や個人の信用が損なわれたりするケースは少なくありません。そんなとき「削除してほしい」と思っても、実際にどう動けばよいのかわからない人も多いはずです。本記事では、ネット上の誹謗中傷に対して削除申請ができるのか、そしてその具体的な手順や注意点について、初心者にもわかりやすく解説します。
誹謗中傷が削除対象となる判断基準とは?
ネット上の悪口や中傷が「削除対象」となるかどうかは、その内容や投稿先のガイドラインによって大きく異なります。一般的に削除が認められるのは、名誉毀損、プライバシー侵害、侮辱、業務妨害など、法律や各プラットフォームの規約に違反している場合です。たとえば、「〇〇は詐欺師だ」「あの会社は倒産間近」など、社会的評価を著しく低下させる表現や、事実無根の断定的な批判は、名誉毀損に該当する可能性があります。
また、個人情報の暴露や、特定の個人や団体への悪意ある攻撃、脅迫・差別的表現なども削除申請が通りやすいケースです。ただし、単なる意見や感想(例:「サービスが悪かった」「期待はずれだった」)については、表現の自由の範囲内と見なされることが多く、削除が認められにくい傾向があります。
削除基準は「事実かどうか」よりも、「社会通念上許容される範囲かどうか」「投稿が社会的信用や権利を不当に侵害していないか」が重視されます。各サービスのガイドラインや削除ポリシーも必ず確認し、自分のケースがどこに当てはまるかを事前に整理しておくことが大切です。
削除申請が可能なプラットフォームと依頼の流れ
インターネットには多種多様な投稿先があり、削除申請の方法や難易度もプラットフォームごとに違います。たとえば、X(旧Twitter)、Instagram、FacebookなどのSNSでは、各投稿ごとに「報告」ボタンが用意されており、理由(誹謗中傷・プライバシー侵害・スパム等)を選択して申請することができます。
Googleマップや食べログ、Amazonレビューなどの口コミサイトも、ガイドライン違反があれば削除申請フォームから対応を依頼できます。特にGoogleの場合は「Googleビジネスプロフィール」から該当する口コミを選び、「不適切なレビュー」として報告する手順となります。掲示板やまとめサイトの場合は、サイトごとに削除依頼の専用窓口や申請フォームが設けられています。
削除申請時に重要なのは、「どの投稿を・どんな理由で削除してほしいのか」を明確に伝えることです。投稿のURLやスクリーンショット、具体的な日時や内容など、客観的な証拠を揃えておくと対応がスムーズになります。対応には数日~数週間かかる場合もあるので、申請後は定期的に進捗を確認しましょう。
削除されないときに取れる次のステップと注意点
削除申請をしても、必ずしも希望どおりに削除されるとは限りません。プラットフォームの判断基準に合致しない場合や、「表現の自由」として認められてしまう内容は、そのまま残されてしまうこともあります。また、海外運営のサービスや、管理体制が緩い掲示板などは削除対応が遅かったり、まったく対応してくれなかったりする場合も少なくありません。
このような場合、次の手段として考えられるのが「法的措置」です。まずは弁護士に相談し、名誉毀損やプライバシー侵害に該当するかどうかの確認を行いましょう。必要に応じて、プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」を行い、投稿者の特定や損害賠償請求に進むことも可能です。
また、削除が難しい場合でも「逆SEO」(ネガティブ情報の検索順位を下げるための対策)や、公式サイト・SNSでの正確な情報発信によるイメージ回復など、できることは多くあります。長期戦になるケースもあるため、焦らず粘り強く対応していくことが重要です。
自分で削除申請するか、専門家に依頼するかの判断基準
削除申請は自分でできる場合も多いですが、内容や状況によっては専門家(弁護士や風評被害対策会社)に依頼する方が確実なこともあります。判断基準としては、「内容が明らかに名誉毀損や違法性を含む」「削除申請を何度出しても通らない」「投稿が大規模に拡散されている」「個人や会社への実害が大きい」といった場合は、専門家の力を借りるべきです。
弁護士に依頼することで、法的根拠をもって削除要請ができ、場合によっては裁判所を通した仮処分や損害賠償請求まで進めることも可能です。また、専門の業者であれば、検索順位対策やネガティブ情報の押し下げ、モニタリングまで包括的にサポートしてくれるところもあります。
一方で、単なる一過性の悪口や、拡散が広がっていない場合は、自分で削除申請を行い、経過を見守るのが現実的です。自分で対応できる範囲を見極め、無理をしないことも大切です。
まとめ
ネット上の誹謗中傷や悪口は、誰もが被害者になる可能性があります。削除申請は多くのケースで自分でも可能ですが、内容や状況によっては専門家の力が必要になる場合もあります。大切なのは、どんな投稿が削除対象になるかを知り、証拠を揃えて冷静に対応すること。そして、粘り強く対応しながらも、必要に応じて法的措置やプロのサポートも検討することが、被害拡大の防止と心の安心につながります。